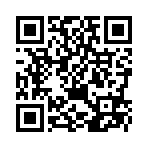2012年06月05日
映画「ちいさな哲学者たち」

映画「ちいさな哲学者たち」をDVDで鑑賞しました。
フランスのとある幼稚園で実験的に行われた「哲学の時間」。
3歳児の時から5歳児までの2年間のドキュメントです。
「哲学の時間」には
毎回、先生が決めたテーマを、みんなで議論をしていきます。
フランスのちびっ子版「白熱教室」です。
テーマは、「愛」、「死」、「違い」、「自由」など
大人にもむずかしいものです。
はじめ、子どもとたちは、
いきなり「哲学の時間」と言われても何をしていいのか分からない様子。
先生の「頭の中で考えていることを伝えるには、どうすればいい?」という質問に、
子どもたちの答えはありません。
先生が、ヒントを与えようと、「口の役割は?」と尋ねると
1人が「話すこと。」と答え、
他の1人が「食べること。」と答えると、
もう1人が「食べながら話しちゃいけないんだよ。」と
思いつくことを気ままに話してしまいます。
回が少し進んで、
「死とは何か」を話し合っている時に、
ある女の子が、
「ママやパパ、おじいちゃんやおばあちゃんが
死んでしまうと考えると悲しい。
親戚のお姉ちゃんやお兄ちゃんが
死んでしまうと考えても悲しい。」と発言した横で、
男の子が、
「親戚、多いんだね。」(←そこですか
 )と
)と筋とは関係ない突っ込みをいれるよう感じで、
子どもたちは、テーマとは関係ない話にそれたり、
人の話を聞いていなかったりします。
この子どもたちが、徐々に人の意見を聴き、
自分で考え、自分の意見を組立て、主張できるようになる。
その過程に引き込まれました。
子どもは、大人と比べ知識と経験が少ないだけで、
考える力や人の話を聴く力、
様々な力は、大人と何も変わらないのだという思いを強くしました。
子どもたち1人1人を1人の人間として尊敬し、
適切な支援を続けていくことが大切なのですね。
最後の授業の時に、
先生が、子どもたちに「哲学の時間」の感想を聞きます。
「『哲学の時間』がなくなってしまうので小学校に行くのはいやだ。」という子、
「考えるのは空想することと同じで楽しい。」という子
「考えるのが好きになった。」という子、もいましたが、
「哲学は嫌い。考えるのに長い時間がかかるから。」という子、
「女の子は、すぐに『考えて!』というから、いやだ。」という子もいる
予定調和的でない終わり方

考えることに対する様々な受け止め方も
大人の世界といっしょなので微笑ましくなりました。
アーチを組める台形の積み木「 A R C H .」
熊本市現代美術館 ・ 通信販売 にて、お求めになれます。
詳しくは、「 A R C H .」のホームページにて。
↓の画像をクリックしてください。


通信販売は、左の「オーナーへメッセージ」からも受け付けています

Posted by ヴェリタス at 05:48│Comments(0)
│日々のいろいろ